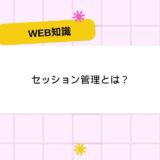Web知識を知っている人
W3Cについて知りたいという方はいませんか?
そこでこの記事ではW3Cについて詳しく解説していきたいと思います。
気になる方は是非最後まで読んで頂けたら幸いです。
\1分で登録完了! 受講料98,000円がなんと0円!/
【期間限定】ノーリスクで学びたい方におすすめ!
以下のプログラミングスクールもオススメです。
是非検討してみてはいかがでしょうか?
- 侍テラコヤ(初月50%OFF学び応援キャンペーン実施中)(解説記事はこちら)
⇒ 学び応援キャンペーンでお得に申し込む!
・コスパ最高! 月額2,980円〜利用できる!
・単月定額と比べて総額最大44,400円OFF!
・学び応援キャンペーン実施中!
- ZeroPlus Gate(受講料98,000円がなんと0円!)(解説記事はこちら)
⇒ 受講料0円でプログラミングを学ぶ!
・受講料0円
・現役エンジニアに質問し放題
・30日で副業レベルのWebスキルを学べる - 本気のパソコン塾
(無料体験特典3つあり)(解説記事はこちら)
⇒ 7日間無料体験または無料相談会に申し込む!
・実際に役立つウェブデザイン、ウェブプログラミングを身につけることができる
・【期間限定】無料相談会参加特典3つあり!
・7日間無料体験・無料相談会実施中!
Web知識を知っている人
目次
W3Cとは?
Web知識を知っている人
W3CはWorld Wide Web Consortiumの略でHTML、CSS、XMLなどWeb関連の標準仕様を策定し、勧告している非営利団体のことです。
W3Cは「World Wide Web Consortium」の略称で、「ダブリュー・スリー・シー」と呼ばれています。
W3Cが勧告している仕様をWeb標準と呼ぶこともあります。
W3Cの解説
HTMLやCSSなどの世界中で広く使われている仕様をブラウザベンダーが各々拡張したり、変更したりすると同じHTMLドキュメントを表示させているのに表示の仕方が変わってしまうケースが出てきてしまいます。
実際に1990年代にはMicrosoftとNetscapeでブラウザ開発競争が起き、MicrosoftとNetscapeが各々のHTMLやCSSの機能を拡張したため、両者のブラウザで同じようにWebページを表示させるのが困難になりました。
そこで重視されるようになったのが、Web標準と呼ばれるものです。
第三者機関であるW3CがWeb標準と呼ばれる仕様を策定し、各ブラウザがこの仕様を守ることで同じHTMLドキュメントは同じように表示されるようになります。
このようにW3Cが策定、勧告している技術がすべてWeb標準として受け入れされてそうですが、必ずしも市場に受け入れられず普及しなかったということもありました。
例えば、W3Cが勧告しているSOAP(Simple Object Access Protocol)を挙げることができます。
以下の表はW3Cが勧告していた技術の一例です。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| HTML | Webページに記述する言語 |
| XHTML | XMLの仕様に沿ってHTMLの機能を実現した言語 |
| CSS | HTMLやXMLのスタイルを指定する言語 |
| Web Fonts | Web上のフォントを変える技術 |
| XML | 拡張性の高い言語 |
| DOM | HTMLやXMLを操作する言語 |
| RDF | リソースを記述するためのXML技術 |
| XML Schema | XML文書の構造定義する言語 |
| XSLT | XMLからXML文書に変換する技術 |
| MathML | XMLで数式を記述するための言語 |
| SVG | ベクターグラフィックを表示するための言語 |
| SOAP | XMLを用いてソフトウェアがデータ通信をするための規格 |
| WSDL | WebサービスをXMLベースで記述する |
| OWL | Webのオントロジーを記す言語 |
| GeoLoacation | 位置情報を扱うためのAPI |
W3Cは上記の技術をワーキンググループで策定しています。
各ワーキンググループは必要に応じて組織され、必要がなくなれば解散するという仕組みになっています。
ワーキンググループは仕様策定時、作業草稿を作り、有識者にレビューされ、問題があれば修正していくという流れになっています。
レビューをして問題がなければ、勧告候補と呼ばれるステータスで公開され、実際にその仕様を実現したプログラム作成を行うように依頼をします。
そして、仕様に問題ないようであれば、勧告案というステータスになります。
こうして様々なレビューを受けて必要だと認められると勧告というステータスを得て、Web標準と認められるようになります。
入門的なWeb知識を習得したい方へ
Web知識を知っている人
初学者がいきなりWebに関する専門書を読み始めると挫折することが多いです。
そこで途中で挫折せずに最後まで読み切れて、Webの全体像を把握するのに便利な一冊になっています。
この本は初めての方にも読みやすいように見開き1ページで文章と図を織り交ぜて端的に解説されています。
この本で全体像を理解してから専門書を読むと取り組みやすいかと思います。
もし、Webに関する入門的な知識を幅広く知りたいと思った方は「この一冊で全部わかるWeb技術の基本」を是非読んでいただければと思います。
Web知識を知っている人
まとめ
Web知識を知っている人
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。
この機会に是非Web知識を習得してみてはいかがでしょうか?
 押さえておきたいWeb知識
押さえておきたいWeb知識